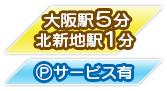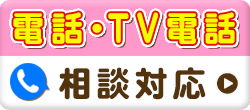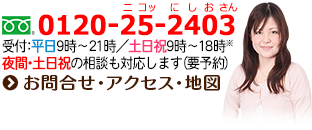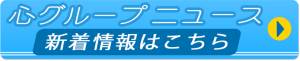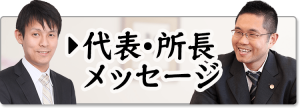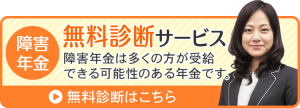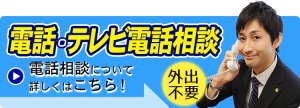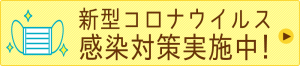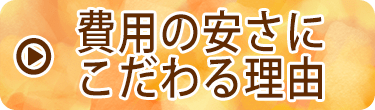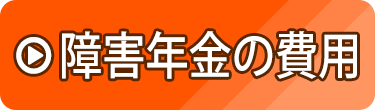障害年金の時効
1 時効について
時効とは、ある状態がそのまま長い期間経過した場合、その期間の経過を理由に、その状態に元々法律上の根拠があった否かにかかわらず、その状態を法律上の根拠があるものとしてしまう制度です。
このような説明だけを聞くと、何のことか分かりづらいかもしれませんが、例えば、刑事ドラマなどで、犯罪をした人が、長い期間、警察に逮捕されず処罰もされなかった場合に「時効だから、もう処罰はできない。」という結論になるシーンをご覧になったことのある方は多いのではないでしょうか。
時効とは、このように、もともとは「法律上はこうあるべきだった。」という状態と、「実際には長い間、事実はこうなっていた。」という状態を比較したときに、一定以上の期間が経過している場合には、元々法律上の根拠がなかった状態でも、その状態を法律上のあるべき姿だと扱ってしまうようになるという制度です。
2 障害年金の請求権について
このような時効の制度は、障害年金においても問題となります。
障害年金は、障害の原因となった傷病について最初に医師の診察や治療を受けた日である初診日から原則として、1年半経過した時点、つまり「障害認定日」以降になれば、受給の請求をすることができます。
本来であれば、この障害認定日を迎えたタイミングですぐに、障害年金の請求をすることが望ましいのですが、様々な理由で、適切なタイミングに請求ができないこともあります。
このような場合でも、障害認定日に本来は年金がもらえるはずだったということを診断書等から証明できれば、後からでもさかのぼって年金の支給を受けることが可能です。
これを障害年金の遡及請求と呼びます。
ただし、このように過去にさかのぼって障害年金を受け取ることのできる権利は、長期間、障害年金を受け取らないままにして放置しておくと、先述した、時効によって「障害年金を受け取っていない状態が法律上のあるべき姿である。」と扱われてしまうことになります。
3 時効の期間について
では、どの程度の期間が経過すると、障害年金をもらうことのできる権利が時効になるかというと、本来、障害年金を請求できるようになってから、5年経過してしまうと、それより以前にもらうことのできた障害年金を受給する権利が時効によって無くなってしまいます。
したがって、障害年金の請求をご検討中の方には、できるだけ早めに、専門家に相談するなどして、手続きを進めることをおすすめいたします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403